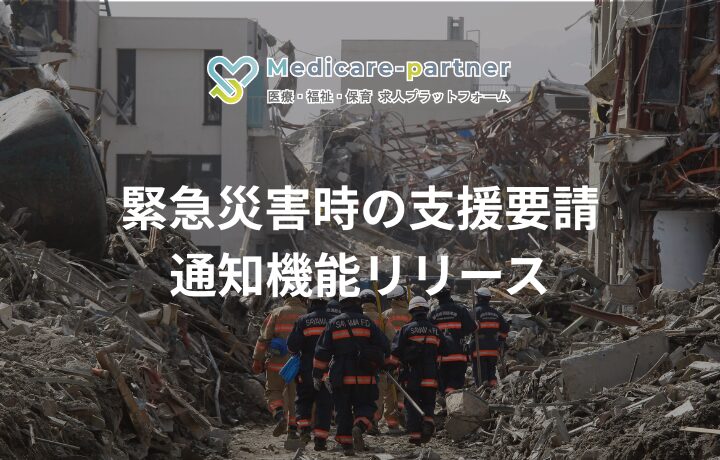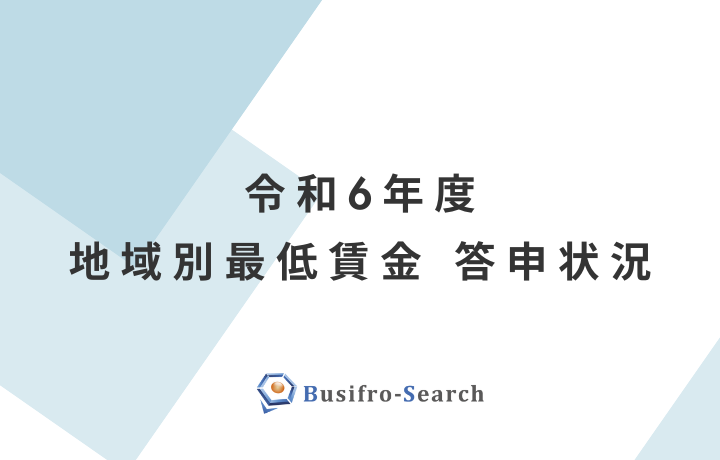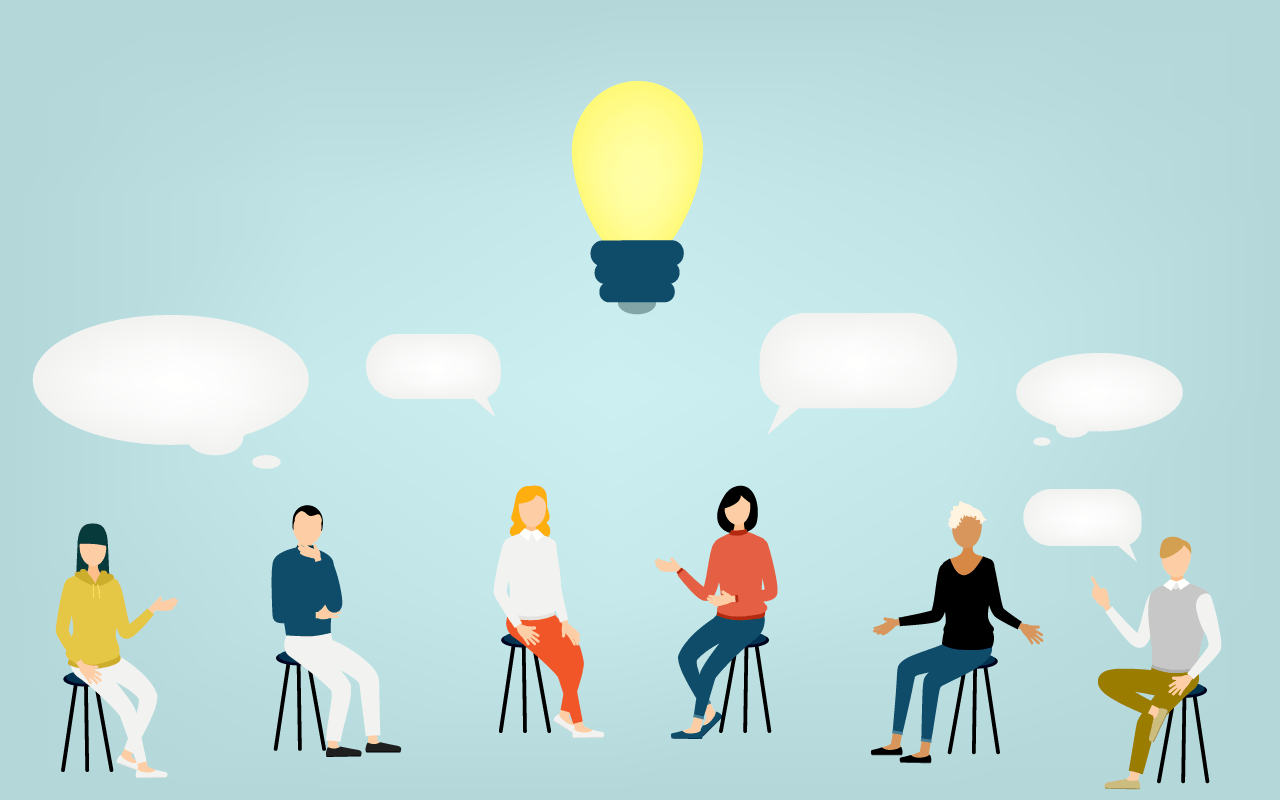厚生労働省は3月17日までに、障害福祉サービスの施設・事業所が利用者を紹介してもらった対価として紹介会社などに金品を支払うのは運営基準違反に当たり、禁止されていることを自治体に周知、徹底した。
サービス利用計画を作る相談支援専門員や、他の障がい福祉事業者に紹介料を支払うことは元々禁じられているが、一般の人や紹介会社の扱いが曖昧だったため、明確化した。自治体の担当課長向けオンライン会議で示した。
障害福祉の利用者紹介を巡っては「日本厚生事業団」(東京)という会社が、紹介業をフランチャイズで展開するとして、加盟企業を募集。障がい福祉の事業所に支払われる公的な報酬(給付金)は、利用者の障害が重いほど高くなるため、紹介料は障がいの程度に応じて設定していた。最も軽い場合は1人当たり20万円、最重度では35万円を目安としていた。 ただ障がい福祉はほぼ公費で賄われているため税金を目的外に使うことになり、サービスの低下につながる恐れもある。
どのようにして利用者の集客はされているのだろうか?
1.オンラインでの集客
✅ホームページの充実
・事業所のサービス内容、特色、スタッフの紹介、利用者の声を掲載
・実際の活動風景やイベントの写真を載せる
・検索サイトなどへの掲載
✅SNSの活用
・FacebookやInstagramで日々の活動を発信
・利用者や家族に役立つ情報を定期的に投稿
・相談会やイベント情報を告知
✅ブログ・SEO対策
・「○○市 障がい福祉」「障がい者施設 見学」などの検索キーワードを意識して記事を書く
・利用者の体験談やスタッフのインタビューを掲載
2.オフラインでの集客
✅チラシ・パンフレットの配布
・役所、病院、学校、支援センターに設置
・地域のイベントで配布
・利用者の家族向け説明会で配布
✅地域イベントや交流会への参加
・福祉関連のイベントやバザーにブースを出す
・地域の交流会や講習会で事業所のPRを行う
✅他の福祉事業所や病院・学校との連携
・相談支援専門員、病院のソーシャルワーカー、学校の先生に事業所を紹介してもらう
・関係機関と定期的に情報交換
✅見学会・体験会の開催
・事業所の雰囲気を直接感じてもらう機会をつくる
・家族や支援者向けに説明会を実施
3.クチコミ・紹介の活用
・現在の利用者やその家族に満足してもらい、自然な口コミを生む
・利用者の家族に紹介キャンペーン(特典を用意)を行う
・スタッフや関係機関からの紹介を促進
4.行政・支援機関との連携
・市役所や福祉課に事業所の情報を登録
・就労移行支援やB型事業所なら、ハローワークと連携
・地域の福祉ネットワーク会議に参加し、事業所を知ってもらう
5、差別化を意識する
・他の事業所にはない強み(専門性の高い支援、独自のプログラム)を明確にする
・事業所の特徴を分かりやすく伝えるキャッチコピーを考える
・成功事例や具体的な支援内容をSNSやブログで発信
上記の集客方法を全てするとかなりに時間や費用がかかり従業員への負担も図り知れません。では、どうすればもっと効率よくできるのでしょうか?
1.ターゲットに直接アプローチできる
ケアベースは、福祉サービスを探している利用者やその家族、支援者が集まるプラットフォームです。そこに登録することで、適切なターゲットに直接アプローチでき、効率的に利用者を増やせます。
2.費用対効果の高い集客ができる
チラシや広告、ホームページ運営に比べて、低コストで広範囲に情報を届けることが可能です。また、オンラインでの集客に不慣れな事業所でも、スマホ1台で簡単に情報を掲載し、利用者とつながることができます。
3.口コミや評判の向上につながる
ケアベース内で利用者や家族からの口コミ・レビューが集まることで、信頼度が向上し、新規の利用者獲得につながります。また、他の福祉事業所とのネットワークを構築することで、(案件マッチング)紹介を受ける機会も増えます。
このように、ケアベースを活用すれば、手間をかけずに効果的な集客が可能になります。まずは無料で登録し、活用を始めてみるのが良いでしょう!

![SMART[スマート]](https://smart-project.jpn.org/wp-content/uploads/2024/09/SMART_LOGO_yoko240911-e1731326081866.png)